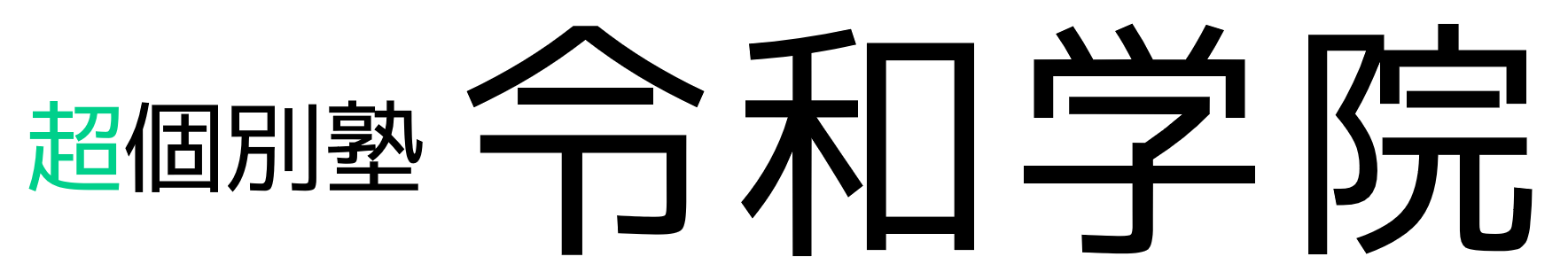目次
① 今年の問題はどうだった?
全体としては「例年と変わりなかった」という印象です。
おそらく平均点も大きく変動しないと予想されます。
ただし、歴史分野では難問も登場しており、「いつもと違う」と感じた受験生もいたかもしれません。
資料問題で初めて見る内容が出るのは近年の傾向であり、これも含めて例年通りと捉えるべきでしょう。

②「歴史」予想外!?
冒頭では「壬申の乱」や「平将門の乱」など、各反乱の背景を問う問題が出題されました。
人物名の暗記だけでなく、時代の流れや出来事の意味を理解していないと解けません。
また、ルネサンスの絵画「三美神」に関する資料問題も登場し、「ヨーロッパの文化史」を理解しているかが問われました。
単語だけでなく、出来事同士の前後関係・ストーリーを押さえることが大切です。
さらに、大正時代の首相「加藤高明」に関する出題もありました。
愛知県出身で、護憲運動と関係の深い人物という情報もヒントになっていますが、大正時代の政治を理解していないと選べません。

③ 「地理」得点源と基礎知識
地理は例年通り、基礎知識で十分対応できる内容でした。
今年は秋田・静岡・岡山・宮崎の4県が登場し、地域が偏らない出題でした。
日本地理では、各県について「気候・人口・特産物」などのイメージを持つことが重要です。
例えば「秋田県=雪が多い・米どころ・人口が少ない」など、基本的なイメージだけでも十分対応可能です。
世界地理では、アジア州を中心に広い範囲が出題されました。
難しい知識よりも、地図上の位置関係や雨温図の読み取りなどが問われた印象です。

④ 「公民」どこまで覚えるべき?
公民は「資料問題」と「司法制度」が中心でした。
資料問題では「インフォームドコンセント」「ユニバーサルデザイン」などの基本用語の意味が問われました。
司法制度の問題は定期テストでも扱う内容であり、刑事裁判・民事裁判の違いや裁判の進め方を知っていれば解ける内容です。
また、経済分野では「公開市場操作」や「円高・円安」に関する出題もありました。
言葉の意味だけでなく、「なぜ行うのか」「どう影響するのか」といった理解が重要です。
⑤ 社会で高得点を取るためには
単純な暗記だけでは高得点は取れません。
用語を覚えたうえで、「背景・理由・結果」といったストーリーを理解することが必要です。
【歴史】
流れ・因果関係・社会の変化を理解しておくこと。
【地理】
各県・各国の「イメージ」を持ち、地図や気候の特徴をセットで覚える。
【公民】
言葉の意味に加え、「なぜその仕組みがあるのか」「どう影響するのか」を理解する。
時事問題にも対応できるよう、ニュースや新聞に日頃から触れておくこと。
────────────
[令和学院 | 名古屋市千種駅前の超個別塾]
https://reigaku.net/
📞お電話: 052-784-8234
📩お問い合わせフォームは こちら
📍愛知県名古屋市千種区今池2-1-6 千種橋ビル2F