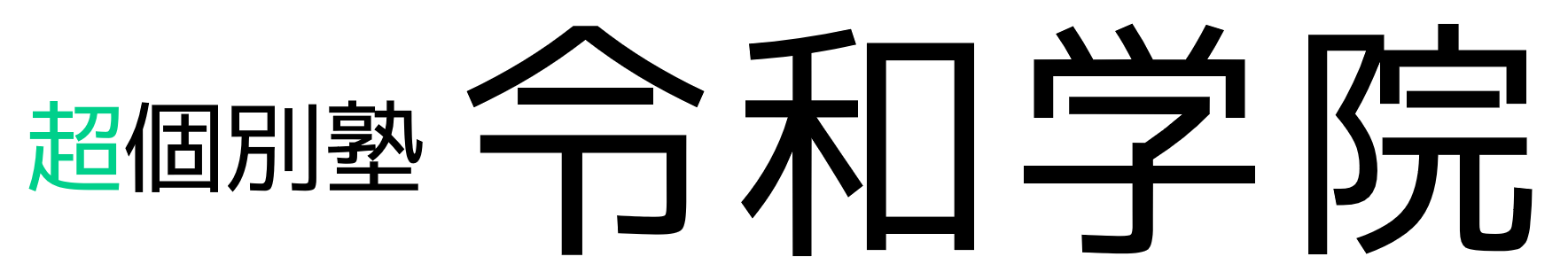近年、生成AIの急速な発展により、教育分野での活用が注目を集めています。特に、OpenAI社のChatGPTなどの生成AIツールは、教育現場での新たな可能性を示しています。
しかし、その一方で、保護者や教育者の間では、子どもの思考力や記述力の低下、AIへの過度な依存、誤情報の受容などの懸念も指摘されています。これらの課題に対し、適切なガイドラインの整備や、教師・保護者の理解促進が求められています。
子どもの学習に生成AIを使うことへの期待と不安
atama plus株式会社が実施した調査によれば、中高生の保護者の約9割が「ChatGPT」を認知しており、子どもの学習への利用意向については、利用意向の高い層(36.7%)が低い層(15.4%)を21.3ポイント上回る結果となりました。
しかし、生成AIの教育利用に対する期待と同時に、不安の声も上がっています。同調査では、保護者が感じる不安として、「子どもの思考力や記述力が育たなくなること」(44.4%)、「AIに依存しすぎること」(43.4%)、「誤った情報や嘘を鵜呑みにしてしまうこと」(36.5%)が挙げられています。
一方で、期待する点としては、「子どもが自身の興味関心を探求すること」(42.4%)や「AIを手段として使いこなす力を身につけること」(37.0%)が示されています。
出典:【保護者453名に聞いた】子どもの学習に生成AIを使わせたい?(atama plus株式会社)
これらの結果から、生成AIを教育に取り入れる際には、適切なガイドラインの整備や、教師・保護者の理解促進が重要であることが分かります。教育現場では、生成AIを効果的に活用し、子どもたちの学びを深化させるための取り組みが求められています。
教育において生成AIを安心して使うために
令和学院では、生成AIを活用した「スクールAI」アプリを導入し、生徒一人ひとりに最適化された学習支援を提供しています。
このアプリは、生成AIの特性を活かし、個別の学習ニーズに対応することで、効果的な学習をサポートします。また、専門家からも「スクールAI」の教育効果や安全性について高い評価を受けており、信頼性の高いツールとして位置づけられています。
出典:専門家の声|スクールAI(株式会社みんがく)
さらに、令和学院では、生成AIの活用に際して、生徒の思考力や記述力を育むための適切な指導を行い、AIへの過度な依存を防ぐ取り組みを進めています。また、生徒と生成AIとの対話内容をスタッフがチェックし、不適切なやりとりや指導内容があれば指導いたします。
これにより、生徒たちがAIを効果的に活用しながら、自主的な学習能力を高める環境を整えています。
まとめ
生成AIの教育分野への活用は、適切な指導とツールの選択により、生徒の学習効果を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
令和学院は、最新の技術を積極的に取り入れ、生徒や保護者の皆さまの安心・安全を確保した上で、生徒一人ひとりの成長をサポートする教育機関として、これからも進化し続けます。